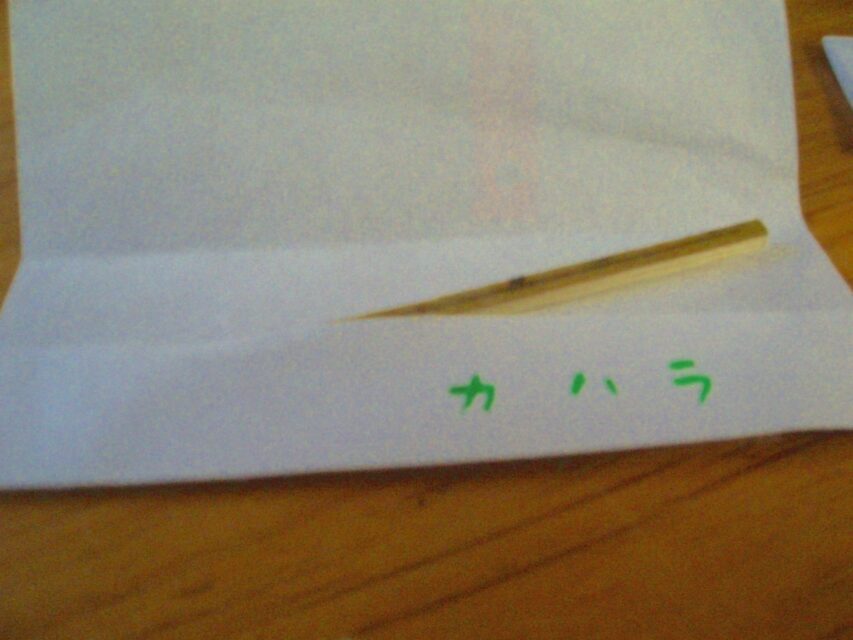カハラ
新地に店を構えて35年。
多くの食いしん坊を誘惑してきた。
たった8席のカウンターに座れた幸運な客たちは、店主 森義文さんが繰り出す食材たちの饗宴に目を細め、歓喜し、唸り、快哉を叫ぶ。
タスマニアペッパーを載せたタスマニア産の生牡蠣に続いて出されたのは、前菜の盛り合わせ。
生しゃこ、吉田牧場のカッチョカバロ薄切り、太白胡麻油和え、肉の香りと共鳴する、驚きのロースとビーフコーヒー風味、じゅんさいとクレソンのスープ、白エビ
続いて 松阪で育てているという 丸々肥えたエスカルゴ。宮崎の風味味噌などのあわせ味噌とコンソメによるソース。味噌味がくどく出過ぎることなく、甘みとコクがほどよく出て、エスカルゴと調和。
写真左奥はパン立て。三個用エスカルゴ器共に特注である。
蒸しアワビとマコモダケの三種タスマニアマスタード和え、バジル風味。
焼フカヒレ。
すばらしい。炊いたふかひれに染みた味わいが深く優しく、なんともうまい。
フカヒレが舌の上でくにゃりと身をよじって、滋味を出す。ちょいと焦げて、カリカリになった端の部分に味が集結して、たまりません。
特殊技術でつけられたという、雪の結晶のように光り輝くローズマリーの塩枝も不思議な品である。
「あーアスパラだ!」
一口飲んだ瞬間、間の抜けた言葉を叫ばしたアスパラのスープ。アスパラと塩と水だけで作った、アスパラの風味が凝縮したスープを、薄い薄い、脆弱な美が漂うベルギーの陶器で。
さあいよいよ主菜。
生クレソンとそばの実サラダに続いてメインイベント 名物の肉のミルフィーユ。
黒塗まな板で映える肉は、一見一枚の切り身のようだが、薄く薄く切った肉を五枚重ねてあるのである。
笑うしかない味である。
表面の香ばしい肉面に歯が当たると、噛むまでも無く歯は肉にめり込んで包み込まれる。脂の香りと肉汁が口いっぱいに溢れ、へなへなとだらしない顔をしていると、脂は何事もなかったかのように消えている。
肉の気品に圧倒されて、力が抜けた。
付け合せは ザーサイの炒めと、金時草、ジャンボマッシュルーム。
閉めはそら豆ご飯。
「そら豆ご飯を用意しましたが、どれくらい食べられますか」と聞かれ、「普通で」、「少なめで」と両隣が答えているのに、「たくさんいただきたい」とわがままをお願いした。
ちなみに左が大盛り。ワタシは丼。
すべてに計算された量の美学を、野暮にぶち破って, 反省しております。
そら豆を炒めて出しと醤油をあわせたタレをかけまわしたご飯である。 さらに進化して、中には温泉玉子が隠されているではないか。
そら豆の甘みと玉子の甘みにご飯がからんで…。
ああもうやめて。
宮崎マンゴーとブランマンジェ(中にはバナナのディタ漬け、上には焦がしたアカシアの蜂蜜をかけて)。
一枚一枚手書きされた楊枝入れ。ビワが描かれた古いロイヤルコペンの蜂蜜さし。その後ろにかすかに見えるは、食事史という本の挿絵を焼かせたというタイル版。店主自らが拭き漆した利休箸。手前に傾いたカウンターの足置き。
全てが特別であり、唯一であるが、形に力が入っていない。
これ見よがしでもない。
料理、器、内装 流れる趣、それそれが一定の芯で貫かれ、絶妙なバランスをとっている。
本質を踏まえた人が発揮する創意に、心が素直になる。
食材や器の説明をする、森さんの静かな語り口に凄みを感じながら。