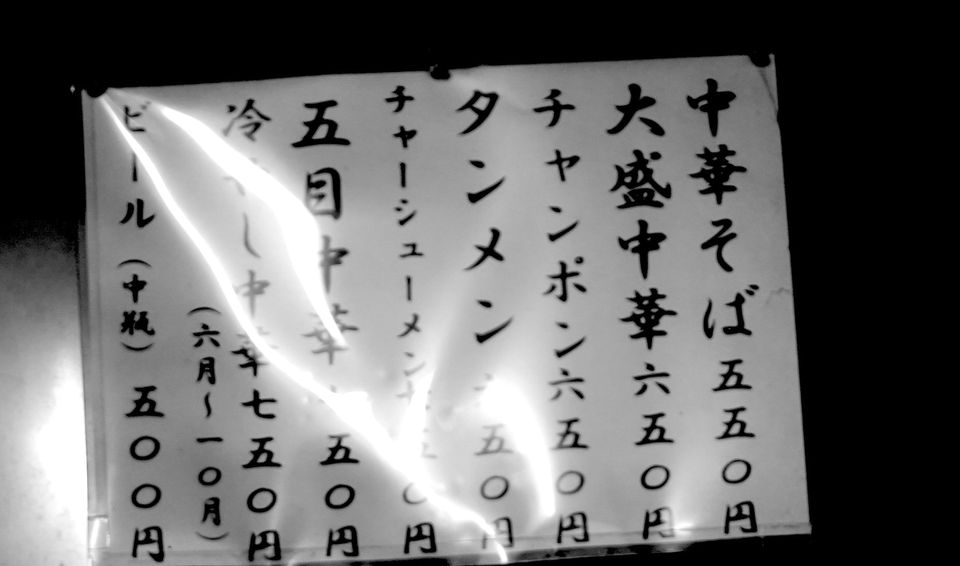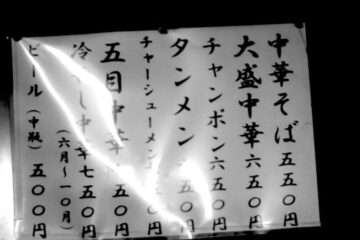褪せた赤のれんをくぐると、細長いカウンターが伸びていた。
剥げかけ、客の愛着が沁みこんだカウンターに座る。
「そばを一つください」
「はいよ」。
奥で座っていた老婦人が、すくっと立ち上がった。
創業を考えれば、おそらく80近いだろう。
しかしどう見ても60くらいにしか見えない。
昔の方なのに、手足が長く、身長も168ほどある。
スラリとした体に黒シャツと黒い腰エプロンをこなし、花柄のベストを着て、金の細いブレスレットと大きな丸いピアスをつけている。
創業は昭和36年だから、もう56年間店を続けられている。
「この店に来た時には、髪が腰まで長くてね」。そう語る女将は、かなりモテただろう。
しかしご主人一筋で、亡くなられた後もこの店を守っている。
「俺はこの店長いんだ」。
隅に座って、ビールをすでに2本も飲んでいた70代の常連客が、突然口を開いた。
「俺はこの店が好きでね。ある時なんか、酔っ払って入ったらね、女将が言うんだ。あんた今夜は3回目だよってね」。
「3回目も、ラーメン食べたんですか?」
「当たり前だ」
きっとこのおやじも、ラーメンだけでなく、女将にほの字で、酔っ払って、つい会いたくなってしまったのに違いない。
「ご主人亡くなってから、ずっと一人なんだよ」と、その常連が言うと
「猫がいたよ」と、女将。
「ああそういえばいたなあ、黒猫が」。
「白だよ」。
女将は中華鍋に入ったお湯を捨てると、またお湯を入れ、火にかけた。
次にチャーシューを切り、細い縮れ麺を中華鍋に渡した木蓋の上に置いた。
湯が沸くと、麺を入れ、ナルトを切る。
さらにスープを丼に注ぐ。
次にネギを切り、麺を湯から上げて、湯切りする。
麺をスープに入れて、具をのせ、我々の元へ運ばれた。
仕込みをせずに、注文を受けてから切り、整える。すべてがアラ・ミニッツである。
このことがいかに誠実であるのか。
この商売で、お金をいただくという感謝と意味を知っている。
そのラーメンだが、スープを一口飲んだ途端に、「はぁ」と力が抜ける、昭和のラーメンである。
温かみが漂う醤油味の味のスープをまとって、麺が勢いよく唇をすり抜ける。
切りたてのネギは香り、じっくり低温で煮た(低温調理だ)というチャーシューは、身をうっすらとピンク色に染め、しっとりと肉汁を含んでいる。よくよく煮たシナチクに。噛みしめる喜びがある。
ほどよくうまく、ほどよく普通という品格がある。
それが、しみじみとした余韻を残す。
小学生からお年寄りまでが、同じく得られる小さな贅沢が、静かに静かに存在している。
ラーメンとはなにかという答えが、ここにある。
長野「白水」にて